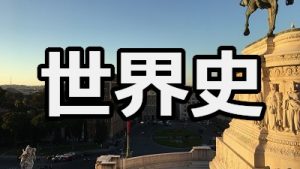こんにちは、歴くまです!
源頼朝、足利尊氏、徳川家康と言われたら、誰もが一度は聞いたことがあると思います。
彼らはそれぞれ鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府の初代将軍、つまり幕府を開いた人です。
しかし、彼らの息子で、二代将軍である源頼家、足利義詮、徳川秀忠は父たちと比べると知名度に欠けます。
むしろ、彼らの弟や息子である三代将軍の方が、知名度が高いです。
今回は、そんな影が薄い将軍家の二代目たちに迫りたいと思います。
非業の死を遂げた 源頼家

寿永元年(1182年)、頼家は源頼朝と北条政子の間に生まれます。
待望の男児であった頼家は、頼朝の後継者として周囲の期待を一身に受けながらすくすくと成長し、誰もが認める武芸の達人となります。
しかし建久10年(1199年)、頼家が18歳のとき、父頼朝が急死します。
頼家は父の跡を継ぎ、『鎌倉殿(鎌倉幕府の棟梁)』となりますが、それから3カ月後、頼家は鎌倉殿の権利であった訴訟を裁断する権利を剥奪されてしまいます。
原因は頼家が公平ではない恣意的な判断を下すことが多かったからだと言われていますが、真偽は不明です。
結果、裁断は頼家の祖父、北条時政を含めた13人の合議を通すことになりました。
頼家はこれに反発し、妻の一族である比企氏を重用するようになります。
建仁3年(1203年)、頼家は病にかかり危篤状態に陥ります。
このとき、頼家が存命であるにもかかわらず、鎌倉から「頼家が病死したので、千幡(頼家の弟、実朝)が後を継いだ」との報告が都に届きました。
北条氏はこの時、頼家を亡き者にする覚悟を決めていたのでしょう。
北条時政は、まず頼家の舅であり、かつその後ろ盾でもあった比企能員を殺害。
そして、自らの曾孫でもあった頼家の子、一幡も殺してしまいました。
戦乱の世で親兄弟が殺し合うことはあったでしょうが、幼い曾孫にまで手をかけるとは…。
頼家はこれに激怒し時政討伐を命じますが、従うものは少数でした。
結局、頼家は伊豆の修善寺に護送され、北条氏によって殺害されます。
享年23、頼家の4人の男子はみな非業の死を遂げ、一人娘の竹御所の死によって頼朝と政子の血筋は断絶してしまいました。
人質から将軍へ 足利義詮

義詮は生まれてすぐ、3歳のときに北条氏の人質となりました。
父である足利尊氏が鎌倉幕府に反旗を翻すと鎌倉を脱出し、尊氏と並ぶ実力者であった新田義貞の軍勢に合流して鎌倉を攻めることになります。
この時、鎌倉攻めに参加した武士に対し、父の名代として軍中状(軍功を立てた証明書)を発付し、このことが、足利家が武家の棟梁とみられるきっかけになりました。
後醍醐天皇による建武の新政では、鎌倉に置かれ、尊氏が後醍醐天皇から離反すると南朝(後醍醐天皇方)に対抗して鎌倉から東国を支配しました。
尊氏が幕府を開きしばらくすると、足利家の執事である高師直と尊氏の弟直義の間に対立が起こり、直義は失脚します。
これにより、義詮は鎌倉から京都へ呼び出され、父の政務を助けることになります。
正平13年(1358年)、尊氏が亡くなり、義詮が後を継いで征夷大将軍となりますが、南朝勢力は健在で、政権は安定しませんでした。
そこで、西国の雄であった山名氏や大内氏を領土の安堵という条件を持ち出して帰順させ、さらに南朝との講和も行い、政権を安定させることに成功しました。
正平22年(1367年)、義詮は幼少の息子である義満を管領(将軍を助け、政務を総轄する役職)の細川頼之に託し、この世を去ります。
享年38、息子の義満は室町幕府の最盛期を築き、観光名所の金閣寺を建てることになります。
凡庸ゆえに後継者に選ばれた 徳川秀忠

秀忠は徳川家康の三男でしたが、長男信康は織田信長の要求により切腹、次男秀康は結城氏の後を継いだため、秀忠が実質的に後継者として目されるようになりました。
しかし、天下分け目の関ヶ原の戦いにおいて、秀忠は真田昌幸・幸村親子によって上田城に釘付けとなり、関ヶ原本戦に間に合うことができませんでした。
このことがあったからか、関ヶ原の戦いの後に家康は諸将を集めて後継者を決める会議を開きます。
家康の参謀、本多正信は次男の秀康を支持、武将の井伊直政や本多忠勝は四男の忠吉を推します。
しかし、ただ一人、大久保忠隣が「乱世においては武勇が肝要だが天下を治めるには文徳も必要。知勇と文徳を持ち謙譲な人柄の秀忠様しかいない」と秀忠を推しました。
忠隣は三方ヶ原の戦いで武田信玄に敗れて徳川軍が散り散りになる中、脱糞しながら浜松城へ逃げ帰った家康の傍を離れなかった忠臣です。
その忠隣が推したということもあってか、家康は秀忠を後継者とします。
慶長8年(1603年)に幕府を開いた家康は、2年後には将軍職を秀忠に譲り、将軍職を徳川家が世襲することを世に知らしめました。
父家康が没した後は政務を執り、できて間もない江戸幕府の安定化に努めました。
寛永9年(1632年)、秀忠は嫡男家光に後事を託し薨去、享年54。
武将としては凡庸でしたが、治世の才能を家康に見込まれ、江戸幕府の支配を盤石なものとしました。
嫡男家光は「生まれながらの将軍」として江戸幕府の頂点に君臨することになります。
まとめ
初代に比べると影が薄い二代目たちですが、父が創り上げた幕府の支配を安定化させようと努めたところに共通点を感じました。(頼家の場合は失敗に終わりましたが…。)
この3人を見てみると、二代目はイケイケの武闘派よりは、おっとりとした穏健派の方が統治は上手くいく気がします。
ちなみに私は、中学生時代に隣にいるにもかかわらず、「歴くま、どこにいんの?」と言われたことがあります…。影が薄かったですね。