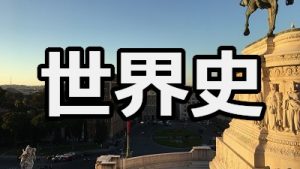こんにちは、歴くまです!
前回記事を書いてから、1か月ほど経ってしまいました…。
なぜこんなに時間が経ってしまったのかというと、ずばり「ゲーム」です。
今までも「Hearts of Iron Ⅳ」にはまっていたのですが、10月に「Call of Duty®: Modern Warfare」が発売されてしまい、これにもドハマりしました。
いつの時代も人々はゲームに夢中になり、時間を忘れるほど楽しんできました。
今回は、そんなゲームはどうやって生まれて発展していったのかを、代表的なボードゲームをいくつか紹介しながら見ていきたいと思います。
世界最古のボードゲーム「セネト」

現状で世界最古のボードゲームと言われるのが「セネト」です。
セネトは、エジプトにまだ王朝が無かった時代の墓から発見されました。
その時代はというと、なんと紀元前3500年頃!世界各地で文明が勃興し始めた頃ですね。
では、なぜセネトはお墓から発見されたのでしょうか?
それは、古代エジプト人が決定論(あらゆる出来事は、その出来事に先行する出来事のみによって決定しているという考え方)を信じ、ゲームに成功したプレイヤーは神々の加護を受けることができる、と考えられていたからです。
そのため、来世への危険な旅の御守り的な意味合いで、セネトが一緒に埋葬された可能性が高いです。
エジプトでは、このような宗教的な意味合いが強かったようですが、セネトが伝搬した周辺国では宗教的な意味合いが弱まり、普通のボードゲームとして遊ばれていたようです。
さて、ゲームの肝であるルールなのですが…、はっきりとは分かっていません。
ただ、投げ棒や骨を投げて駒を進める、2人プレイ用の双六みたいなゲームだったと考えられています。
セネトを再現したゲームも発売されているようなので、よかったら調べてみて下さい。
将棋やチェスの原型「チャトランガ」

一昨年は藤井聡太さんがプロデビューから無敗で29連勝という新記録を打ち立て、大きな話題となった将棋ですが、その原型が生まれたのはインドでした。
そのゲームは「チャトランガ」。伝説では戦争好きの王様に戦争をやめさせるために、お坊さんが献上したと言われています。
チャトランガには二人制のものと四人制のものがありますが、二人制のものはかなりチェスに似ています。チェスでいうと、クイーンとビショップ以外の駒は、チャトランガの駒と同じ動きです。
将棋でいう「持ち駒(とった駒を自分の駒として使える)」の概念がないのも似ていますね。
四人制のチャトランガは、最初に見て「あれ、これ一人が他の三人にいじめられる奴じゃ…。」と思ったのですが、どうやら二人が一組になって組同士で戦い、そのあとに勝った組の二人が戦うというトーナメント方式だったようです。
たしか「こち亀」の100巻あたりで四人制の将棋を両さんが考案してやっていたような。最終的に派出所のメンバーに「反両さん連合」を組まれてボコられていた気がしますね(笑)
まあそんなこんなでチャトランガはインドを飛び出し、ペルシャではシャトランジ、ヨーロッパではチェス、中国では象棋(シャンチー)、日本では将棋と世界各国で派生形が誕生することになります。
三国志の軍神、関羽も好んだ「囲碁」

最近の話題だと、10歳の仲邑菫さんが囲碁のプロ棋士となり、ニュースなどで取り上げられました。
そんな仲邑菫さん、見た目は可愛い女の子ですが、囲碁を打っているときの表情は勝負師のそれです。
そう、囲碁はとても奥深いゲームなのです。
囲碁の起源は明確になってはいませんが、中国の占星術が変化して誕生したと言われています。その名残からか、盤上に九つある点を「星」と呼びます。
囲碁はチェスや将棋と異なり、線が交差している交点上に石を置いていきます。黒石と白石を交互に打ち、一度打った石は移動させることができません。
現在は19路盤(交点の数が19×19)ですが、三国志の頃は17路盤だったと考えられています。
三国志の英雄関羽には、囲碁にまつわる有名なエピソードがあります。関羽は敵将から毒矢を受け、骨まで毒がしみ込んでしまいました。そのため、肘を切開して骨を削り取らなければならなかったのですが、なんと関羽は手術を受けながら平然と囲碁を打っていたそうです。
時は流れて2016年、コンピュータ囲碁プログラムと伝説的棋士の対決が実現します。AlphaGo(アルファ碁)対李世乭(イ・セドル)の五番勝負です。
前評判では圧倒的に李世乭が強いと思われていましたが、いきなり三連敗し負け越しが確定。コンピュータ囲碁が人間の強さを超えたとこと、そして残り二局もどうせコンピュータが勝つだろうという雰囲気が漂い始めます。
迎えた第四局、誰もがAlphaGoの勝利を予想する中、李世乭は諦めていませんでした。そして78手目、李世乭の「神の一手」が炸裂し、AlphaGoは敗北します。これが、世界最強のコンピュータ囲碁プログラムに、人間が勝利した最後の対局となりました。
老若男女みんなに親しまれる「オセロ」

最後はどんな世代にも人気の「オセロ」で締めたいと思います。
挟んだ石をひっくり返すという単純明快なルールのオセロですが、果たしてオセロが生まれたのはいつなのでしょうか?紀元前3000年か、はたまた2000年か…。
実は、オセロが生まれたのは1970年代!誕生から50年ほどしかたっていないんです!
しかもオセロを作ったのは日本人の長谷川五郎さん!この方、製薬会社の社員だったそうです。
ボードゲームが好きで、囲碁・将棋ともにかなりの腕前。そのことを聞いた同僚の女子社員から「何かゲームを教えて!」と頼まれますが、ルールが複雑で中々上手くいかない。
そこで長谷川さんは、学生時代に自信が考案した「挟み碁」を思い出し、囲碁の「石を囲んだら取れる」というルールを「石を挟んだらひっくり返せる」というルールにして女子社員に教えたところ、ルールが簡単なのですぐに理解して、お昼休みに遊ぶようになったといいます。
では、名前がなぜ「オセロ」なのかというと、長谷川さんの父親である長谷川四郎さんが英国文学の教授であり、シェイクスピアの戯曲「オセロ」をゲームの名前にしたらどうかと提案したそうです。
オセロをしていると、愛するデズデモーナを自らの手で殺してしまったオセロの悲痛な叫びが聞こえてきませんか…?
まとめ
現代ではコンピュータゲームが台頭し、パソコンやゲーム機で遊ぶことが多くなりましたが、ボードゲームにもコンピュータゲームとはまた違った楽しさがあります。
セネトのように運の要素が入るゲームもあれば、チャトランガ、囲碁、オセロのように運の要素が介在しない、実力100%のゲームもあります。
モニターばかり見ていて目が疲れてきたら、たまにはボードゲームをしてみるのもおすすめです。