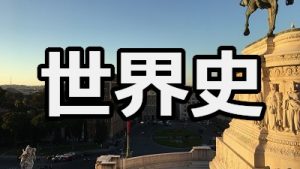こんにちは、歴くまです!
突然ですが、日本最古の時計ができたのは一体いつでしょうか?
正解は…、なんと飛鳥時代!
遣唐使によりもたらされ、大化の改新を成し遂げた中大兄皇子(後の天智天皇)が作らせた「漏刻(ろうこく)」という水時計が日本最古の時計なのだそう。
しかし、中世の日本で時計が使われたという話はあまり聞きません。
日本に時計がもたらされてから、現在のように各家庭に時計が普及するまで、日本人はどのようにして時間を計ってきたのか。
今回は、日本の時計の歴史を見ていきます。
日本最古の時計「漏刻」
さて、冒頭でも述べたように、日本最古の時計は「漏刻」という水時計でした。
これは現代でいうサイフォンの原理を利用したものになっています。
サイフォンの原理とは、ある液体を、管を通して高い位置にある出発点から低い位置へ流そうとするとき、管内が液体で満たされていれば、管が出発点より高い位置を通っても水は流れるという理論です。
この原理で複数の水槽を繋ぎ、一定時間が経ったら水が溜まるという方式で時間を計っていました。
管に異物が入って詰まったり、冬の寒い日に水槽が凍結したりすると正確な時間が計れなくなります。
そこで、漏刻博士と守辰丁(しゅしんちょう)という二つの官職が作られ、彼らが時間を正確に刻めるように時計の管理を行っていました。
日本では、この水時計が長く使われることになります。
乱世と不定期法
中世の日本は、武士の台頭などもあり、戦乱の世となります。
戦で移動する武士たちは、いつもちょうど漏刻のそばにいる、などというわけにはいきません。
乱世では、置時計であり管理も大変な漏刻は有効活用されず、代わって日の出から日の入りを6等分した不定期法が使われるようになります。
お化けや幽霊が出ると言われる「丑三つ時」も不定期法の表現ですね。
余談ですが、不定期法の面白い話に、落語の「時そば」があります。
二八そばを食べに行った男が、お勘定をごまかすという話です。
男はテンポよく一文銭を払いますが、「1、2、3、4、5、6、7、8」と来たところで、「今なん時でい!」とそば屋に尋ねます。
そば屋が「へい、9つ(午前0時頃)でい」と答えると、男は「10、11、…、16!ごちそうさん!」と一文ちょろまかして行った、という話です。
このように、日本の不定期法には「時鐘(例:暁9つ)」と「辰刻(例:丑の刻)」という二つの表現がありました。
表
では、人々はどのようにして時刻を知ったのでしょうか?
江戸時代以前、人々が時刻を知るために用いていたのは太陽の傾きでした。
季節ごとの太陽の傾きで、感覚的に時刻を読み取っていたのです。
時刻を知らせる時の鐘
徳川家康が天下を統一し、平和な江戸時代が訪れると、時刻を知らせるシステムも整えられます。
江戸では各所に時刻を知らせるための『時の鐘』が設置され、人々はその鐘が鳴る回数で「あっ、いま○時だな」と時刻を知ることができたのです。
江戸での鐘のつき方は特徴的で、時刻を告げる時打ちの鐘をつく前に、「捨て鐘」と呼ばれる鐘を三度ついていました。
この鐘をうつことで人々の注意を引き、時刻の聞き間違えを無くすためのシステムでした。
そしてもう一つ、時の鐘をうつ人の聞き間違えを無くすという意味もありました。
時の鐘は、鐘の場所によってうつ順番が決まっており、誤った回数鐘をうってしまったり、鐘をうつのが遅かったりすると、厳しい罰を受けさせられました。
現代でいうと、腕時計が1時間遅れたりするイメージです。そんなことがあったら、とても困りますよね。
さて、江戸で発達したこの『時の鐘』システムですが、日本全国へ拡大していき、鐘の鳴らない所はなかったと言われるほどです。
日本の鉄道の時刻が欧米と比べて正確なのは、この『時の鐘』システムが日本人の根っこにあるからかもしれません。
独自に発達した日本の時計
江戸時代は時の鐘をうつ時報システムが発達したと述べました。
では、最初の時の鐘は何を基準にうたれていたのでしょうか?
それは、『和時計』と呼ばれる機械式の時計です。
日本に機械式時計がもたらされたのは室町時代、スペインの宣教師フランシスコ・ザビエルが、戦国大名の大内義隆に「自鳴鐘」と呼ばれる時計を献上したと伝えられています。
これらの時計は定期法(1日の長さを等分して時間を決める方法)であり、不定時法の日本で使えるものではありませんでした。
しかし、そこは手先が器用な日本人!なんと、不定時法に合わせた時を刻む時計を作ってしまうのです!
この和時計を基準に時の鐘がうたれ、江戸時代の日本人は正確な時間を知ることができたのです。