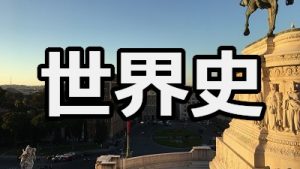こんにちは、歴くまです!
- 弘文天皇
- 淳仁天皇
- 仲恭天皇
突然ですが、この3人の天皇の共通点は何でしょう?
正解は…、「明治時代まで天皇とは見なされていなかった」という点です。
そう、彼らは明治時代になるまで「○○天皇」とすら呼ばれなかった、悲劇の天皇たちなのです!
今回は、そんな彼らの生涯について見ていきましょう。
弘文天皇(大友皇子)
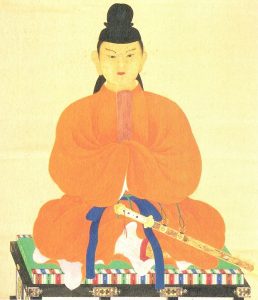
弘文天皇(大友皇子)
まずは弘文天皇ですが、『大友皇子』の方が聞き覚えはあるのではないでしょうか?
大友皇子は、天智天皇の第一皇子として生まれます。
天智天皇は、大化の改新で蘇我入鹿を倒した、あの中大兄皇子です。
蘇我氏を倒すくらいですから、天皇に即位してからの権力は絶大でした。
もともと天智天皇は、弟の大海人皇子を皇太弟としていましたが、大海人皇子は天皇が第一皇子の大友皇子を太政大臣につけたことで、大友皇子を後継者にしたがっていることを察したのか、皇太弟を辞します。
代わって皇太子に選ばれたのは、大友皇子でした。
671年、天智天皇は病に倒れます。
もう長くはないことを悟った天智天皇は、枕元に大海人皇子を呼び、後事を託そうとします。
「これは天皇が、自分が大友皇子に逆らわないか試している」と悟った大海人皇子は、「私には無理です、俗世を捨てて山に籠ります」と僧侶になり、吉野へ行きます。
翌年、天智天皇は崩御し、大友皇子が後を継ぎます。
それから半年もたたないうちに、大海人皇子は反乱の準備を開始。
東海地方の豪族を味方に付けると、東国へ続く要衝であった不破関を封鎖して、東国から軍隊を集めることに成功します。
一方、大友皇子も兵を募りますが、東国は大海人皇子に抑えられ、西国の栗隈王からは外国からの攻撃への備えを理由に出兵を断られます。
それでも周辺国から大海人皇子の軍勢と同等の兵力を集めることに成功します。
決戦が行われたのは近江の瀬田橋、結果は大友皇子の大敗でした。
敗れた大友皇子は自決。享年24。
治世が半年と短く、即位関連の儀式も行えなかったことから、長らく天皇には数えられていませんでした。
淳仁天皇(淡路廃帝)

淳仁天皇の父・舎人親王
淳仁天皇は、先代が孝謙天皇、次代が称徳天皇(孝謙天皇が重祚)と、強烈な女帝に挟まれて影が薄い人物です。
まず、淳仁天皇がどんな人だったかというと、当時から影が薄い人物でした。
大炊王と呼ばれていた淳仁天皇は、天武天皇の第六皇子・舎人親王の七男として誕生します。
天皇の孫でありながら官位は無く、天皇になるまでは全く注目されていませんでした。
そんな大炊王に狙いを定めたのが、藤原仲麻呂です。
注目度ゼロの大炊王はかえって扱いやすいと思われたのか、仲麻呂は大炊王と粟田諸姉(仲麻呂の長男・真従の未亡人)を結婚させて、自分の屋敷に住まわせます。
仲麻呂は、自分と関係が深い大炊王を孝謙天皇に強くアピールし、大炊王は皇太子となります。
天平宝字2年(758年)、孝謙天皇は体調不良と母である光明皇太后に仕えるという理由で、大炊王に譲位します。
これが、淳仁天皇です。
ここまでは、注目されていなかった皇族が、権力者の力を借りて天皇になるというサクセスストーリーです。
しかし、孝謙上皇が僧侶・道鏡を寵愛し始めると、事態は一変します。
道鏡をよく思わない仲麻呂は、淳仁天皇に孝謙上皇を諫めることを勧めます。
淳仁天皇は仲麻呂の言ったとおりに、孝謙上皇に道鏡を遠ざけるよう説得しようとしますが、「ふざけんな!」と一蹴されてしまいます。
ここから、淳仁天皇と孝謙上皇の関係は急激に悪化し、仲麻呂は孝謙上皇と道鏡に対して反乱を起こします(藤原仲麻呂の乱)。
この反乱は失敗に終わり、天皇は反乱には加担しなかったものの、仲麻呂との関係が深かったことを理由に廃位され、淡路島へ島流しとなります。
ですが、称徳天皇(=孝謙上皇)と道鏡を快く思わない人は多くいたらしく、淳仁天皇は島流しにされた後も影響力を持っていました。
淳仁天皇は逃亡を図るも失敗し、その翌日に亡くなります。
公式には病死とされていますが、タイミング的に称徳天皇が殺害の命令を下した可能性が高いです。
淳仁天皇は、称徳天皇の意向により天皇には数えれられず、淡路廃帝と呼ばれてきました。
仲恭天皇(九条廃帝)

仲恭天皇の父・順徳天皇
建保6年(1218年)、仲恭天皇は順徳天皇の嫡出の皇子として誕生します。
生後1ヶ月で皇太子となり、父・順徳天皇が祖父・後鳥羽上皇と共に承久の乱に参加するために譲位し、わずか4歳で践祚します。
しかし、朝廷軍は北条泰時率いる鎌倉幕府軍に敗北、後鳥羽上皇と順徳天皇は、それぞれ隠岐と佐渡に島流しとなります。
幕府は仲恭天皇を廃位させ、代わりに高倉天皇の孫を後堀河天皇として即位させます。
仲恭天皇は、時の鎌倉幕府の将軍である九条頼経の従兄弟であったことから、周囲も予想外の廃位であったと言われています。
天皇であった期間はわずか78日、在位期間が最も短い天皇です。
天皇は廃位後に母の実家である九条家に引き取られ、17歳でその生涯を閉じます。
彼も、九条廃帝、承久の廃帝、半帝、後廃帝などと呼ばれ、明治時代まで天皇とは認められませんでした。
天皇への復帰
明治政府による天皇号の追諡(ついし、死後におくり名を贈ること)が行われ、三人の天皇には諡号が贈られることになります。
- 大友皇子 → 弘文天皇
- 淡路廃帝 → 淳仁天皇
- 九条廃帝 → 仲恭天皇
この追諡により、三人は天皇へと返り咲くことができたのです。