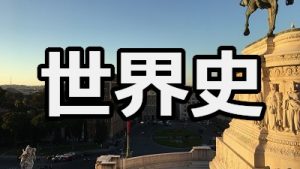こんにちは、歴くまです!
いよいよ大河ドラマ『麒麟がくる』が放送を開始しました!
戦国物の大河ドラマは3年ぶりとのことで、初回の視聴率が19.1%と高視聴率であることからも、ドラマへの期待度が伺えます。
麒麟がくるの主人公である明智光秀と言えば、やはり本能寺の変でしょう。
光秀は、京の本能寺に滞在していた主君織田信長を急襲し、滅ぼします。
今回は、この本能寺の前後にスポットを当てて、織田家諸将の動向と共に、明智光秀の最期に迫りたいと思います。
本能寺の変が起こる直前の織田家諸将の配置

本能寺の変が起こる直前、織田家の諸将は軍団長として各方面に赴いていました。
柴田勝家も、丹羽長秀も、羽柴秀吉も、織田家の重臣はみんな京から離れていました。
それでは、一人一人がどこにいたのか、見ていきましょう。
柴田勝家

織田家最古参の家臣の一人である柴田勝家は、信長から北陸方面軍の軍団長として、上杉家の攻略を命じられていました。
織田家に対して、関東の北条家、東北の伊達家らが恭順の意を見せる中、東における信長の敵対勢力は、越後を本拠とする上杉家でした。
本能寺の変が起こる3ヶ月前、勝家は越中の魚津城に攻撃を開始しました。
攻撃する織田軍は約4万、籠城する上杉軍は約4千。
10倍近い敵に対し、上杉軍は奮戦しますが、天正10年(1582年)6月3日、ついに魚津城は落城します。
信長が本能寺で討たれた、その翌日のことでした。
丹羽長秀

丹羽長秀も柴田勝家と同じく織田家に古くから仕えた家臣の一人で、織田家中では筆頭家老の柴田勝家に次ぐ、No.2の二番家老の地位を与えられていました。
長秀は、本能寺の変の直前には信長の三男である神戸信孝と共に大阪にいました。
信孝を総大将とする、四国方面軍の副将を命じられていたのです。
敵は、四国をほぼ傘下に置いていた長宗我部元親でした。
軍勢を整え、あとは信長が閲兵に来るのを待つだけ…、というその時に本能寺の変が発生します。
運が悪かったのは、長秀・信孝ら方面軍の将が、軍勢がいた住吉ではなく岸和田にいたことです。
住吉は岸和田より京に近いため、信長が亡くなった知らせが長秀たちよりも早く伝わり、四国方面軍は大混乱に陥って四散してしまいました。
羽柴秀吉

羽柴秀吉は貧しい農民の出と言われていますが、信長のもとでその才能をいかんなく発揮し、柴田勝家や丹羽長秀らの重臣と肩を並べるまでになります。
羽柴という名字も、丹「羽」長秀と「柴」田勝家にあやかって一字ずつ取って付けたもので、秀吉の人の懐に入る上手さが伺えます。
秀吉は、信長から毛利氏の支配下にある中国地方の攻略を命じられ、備中高松城を水攻めしている最中でした。
本能寺の変の報を受けた秀吉は、直ちに毛利家と講和します。
備中高松城の城主である清水宗治の見事な切腹を見届けた秀吉は、すぐさま次の行動に移ります。
滝川一益
滝川一益は近江国甲賀の生まれと言われています。
鉄砲の扱いに優れていたことから、織田家に仕えることになったとされています。
信長が甲州征伐を企画し、嫡男信忠を総大将として信濃に攻め込んだとき、一益は家老の河尻秀隆と共に副将として参戦します。
一益は、この甲州征伐で敵の総大将武田勝頼を討ち取るという大功を挙げています。
この功績もあって、一益は関東御取次役の地位を与えられ、関東の平定にあたることになります。
しかし、一益に領国として与えられた上野は今の群馬県にあたり、京からは遠く離れていました。
この地理的なハンデが、本能寺の変後の一益の地位に、大きな影響を与えることになります。
本能寺の変

天正10年6月2日早朝、信長が滞在していた京の本能寺を。光秀の軍勢が取り囲みました。
日本史上最も有名な、そして戦国時代最後の下剋上、本能寺の変です。
各地で方面軍の将として戦っていた織田家の重臣たちと比べて、光秀は圧倒的に信長に近い丹波亀山城にいました。
家老たちが京を離れて各地で戦っているこの時が、信長を討つ千載一遇の好機だったのです。
本能寺を完全に包囲した光秀は、絶対に信長を逃すまいと、寺の四方から攻めこみます。
信長は、弓で応戦するも傷を負い、女房衆に逃げるように指示を出した後、すでに火が回っていた寺の奥へと入っていきました。
「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり」
享年49、50年にはあと1年足りませんでした。
ちなみに「人間五十年~」は、信長が好んで舞ったと言われる『敦盛』に出てくる一説ですが、「人の世の50年の歳月は下天(六欲天の最下位の世)の一日にしかあたらない、夢幻のようなものだ」という意味で、人の一生の期間が50年と言う意味ではありません。
六欲天…仏教用語。天上界のうち、欲望にとらわれている6つの天界を指す。
本能寺の変後の諸将の動き
柴田勝家
魚津城を陥落させた勝家は、信長が亡くなったことを知り、急遽本拠地である北ノ庄城に戻ります。
2018に発見された勝家直筆の手紙には、「光秀は近江いるので、丹羽長秀と連携してこれを討つつもりだ」という内容が見てとれます。
このまますんなりと光秀討伐に迎えていれば、勝家は織田家中でNo.1の地位のままでいられたかもしれません。
しかし、上杉景勝が本能寺の変が起こったことを知り、勝家に奪われていた越中・能登の国人を扇動して、勝家の背後を脅かしました。
この対応に時間を取られた勝家は、本能寺の変から2週間以上たった6月18日に近江に到着します。
ですが、時すでに遅し。
光秀は、羽柴秀吉によって討たれた後でした。
丹羽長秀
さて、長秀と信孝ですが、率いるはずだった軍勢が四散してしまい、織田家臣団の中で最も光秀に近い位置にいたにもかかわらず、光秀を討つほどの軍事力がありませんでした。
そんな中、信長の甥である津田信澄が、光秀に加担しているとの噂が立ちます。
信澄が光秀の娘を娶っていたことが、噂の原因でした。
その噂を信じたのか、長秀と信孝は信澄を攻め、信澄は亡くなります。
しかし、これ以上の軍事的行動はできず、大軍を率いて京に向かっていた羽柴秀吉の軍勢を待つことになります。
羽柴秀吉

信長の死の報に接した秀吉は、早々に毛利家との停戦を取り決め、京へ戻る準備を始めます。
その際、京に近い位置にいた中川清秀には、「信長・信忠は無事である」との偽情報を送り、清秀が光秀側につくのを防ぐなど、準備を怠りませんでした。
そして、十日足らずで備中高松城から京の手前、摂津の富田に到着し、光秀との決戦に備えます。
長秀・信孝と合流していた秀吉の軍勢は、2万にのぼりました。
翌6月13日、秀吉は事実上の総大将(名目上は信孝)として、光秀との決戦に挑むことになります。
滝川一益

本能寺の変後、織田家への対応を変えた
方面軍の将の中で、京から最も遠くにいた一益は、北条氏への対応に苦しむことになります。
信長の死を知った北条氏政は、表向きは織田家と協調関係を続けるように見せかけますが、裏では動員をかけ、攻める気マンマンでした。
また、旧武田領の甲斐と信濃では、武田の遺臣が一揆をおこします。
これにより、森長可は美濃へ逃げ、河尻秀隆は武田の遺臣に討たれました。
6月16日、北条氏は5万を超える軍勢を率いて上野に攻め込んできます。
初戦では辛くも勝利するも、倍以上を誇る北条の兵力を前に、神流川の戦いで一益は敗北。
本拠地である伊勢長島へ退却しようとするも、木曽義昌に行く手を阻まれて人質を渡すなど、散々な目に遭いながら帰還します。
この時、すでに織田家の後継者を決めるために開催された清須会議は終わった後でした。
明智光秀

光秀は本能寺で信長を討った後、すぐに二条御所に立て籠もった信長の嫡男信忠を討ちに向かいます。
信忠勢は奮戦しますが、多勢に無勢。
信忠は自害し、家臣も後を追います。
その中には、光秀と縁戚関係にあると言われた斎藤利治(道三の子)もいました。
光秀は京都の治安維持にあたった後、当時織田家中で最大の勢力を誇っていた勝家に備えるために、近江の坂本城、そして信長の本拠であった安土城を押さえます。
結果論ですが、この対応は秀吉を助けることとなります。
また、味方に付くと思っていた細川藤孝・忠興父子が喪に入るとして光秀になびかず、大和の筒井順慶も当初は山城に兵を出していましたが、裏では秀吉方に寝返っていました。
このような情勢の中、光秀は秀吉より兵力で劣りつつも、決戦を行わなければなりませんでした。
山崎の戦い
光秀が北陸の柴田勝家を警戒して、摂津の国人衆への根回しを怠ったため、摂津の中川清秀、高山右近らは秀吉方につきます。
これにより、秀吉軍は摂津で妨害を受けずに、京に急行することができました。
山崎の戦いは、明智軍の齋藤利三隊・伊勢貞興隊が、羽柴軍の中川清秀隊・高山右近隊に襲い掛かって始まります。
中川隊・高山隊は窮地に陥りますが、池田恒興隊が明智軍の側面を突くと形勢は逆転。
明智軍は離散し、秀吉の勝利が決まります。
光秀は本拠地の坂本城へ逃げる途中、落ち武者狩りに遭い、命を落とします。
三日天下と呼ばれた、明智光秀の悲しい最期でした。
主君信長の仇を取った秀吉の発言力は高まり、織田家の後継者を決める清須会議で、並み居る織田家の重臣たちを抑え込めることになるのです。
まとめ
今回は、本能寺の変前後の織田家諸将の動きを見ることで、明智光秀が羽柴秀吉に討たれることになった経緯を書いてみました。
個人的には、滝川一益の凋落ぶりがなかなか可哀そうだなと思いました。会社だと部長から平社員に降格するくらいのイメージですかね。
なにはともあれ、光秀を討った秀吉は織田家中での発言を高め、信長の後継者に嫡孫の三法師を擁立して天下取りへと歩みを進めていくことになるのです。