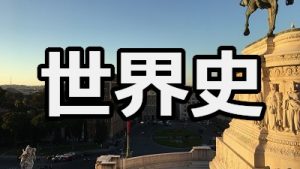こんにちは、歴くまです!
バレンタインデー、それは男子が1年の中で1番ソワソワする日…。
女子は意中の男子に、ドキドキしながら本命チョコを渡す…。
くだらない。
と、いうことで、今回はバレンタインデーの起源になった聖ウァレンティヌスと、バレンタインデーの普及について見ていきましょう。
バレンタインデーの起源はキリスト教の聖人!
バレンタインデーの起源になったと言われるのが、キリスト教の聖人である聖ウァレンティヌスです。
ウァレンティヌスに関する伝説は複数ありますが、代表的なものを紹介します。
まず、ウァレンティヌスを語るには、当時のキリスト教の立ち位置について知る必要があります。
ウァレンティヌスが活躍したのは、3世紀半ばのローマ帝国。
ローマ帝国でキリスト教が公認されるのは、313年のコンスタンティヌス帝のミラノ勅令によってなので、まだキリスト教がローマ帝国から容認と迫害を繰り返し受けていた時代です。
また、この時代は軍人皇帝時代とも呼ばれ、ローマ帝国各地の実力者が皇帝を僭称していた時期でもありました。
そんな軍人皇帝の一人であったクラウディウス2世は、兵士たちが結婚することを禁止します。
理由は、「妻を故郷に残すと、兵士の士気が下がるから」というものでした。
そんなぶっ飛んだ考えを持つクラウディウス2世ですが、皇帝としては比較的有能だったようで、北方から襲来するゴート人やゲルマン人を度々破っています。
さて、結婚を禁じられた兵士たちは、嘆き悲しみます。
まあ当然ですよね、愛する人と結婚できないのに、戦場では頑張って働けと言われるわけですから。
ここで登場するのが、ウァレンティヌスです。
ウァレンティヌスは、兵士たちのために内緒で結婚式を執り行います。
これを耳にした皇帝クラウディウス2世は怒り、ウァレンティヌスに対して「二度と結婚式を行うな!」と命じます。
けれども、ウァレンティヌスは皇帝の命令には従わず、結婚式を行い続けます。
キリスト教の聖人ってけっこう強情なイメージがありますが、ウァレンティヌスもその例にもれなかったようです。(まあ、死を目の前にしても信仰を捨てない強情さがないと、聖人にはなれないとは思いますが)
皇帝の命令に逆らったため、ウァレンティヌスは処刑され、死後に列聖されます。
その処刑の日が2月14日、現在のバレンタインデーというわけです。
繰り返しますが、このウァレンティヌスの話は伝説です。
クラウディウス2世が結婚を禁止したのも史実ではないのでご注意を。
バレンタインデーの前身 ルペルカリア祭
では、なぜこのような伝説が生まれたのでしょうか?
もともと2月14日の前後では、ルぺルカリア祭という古代ローマの神々を祀る行事が行われていました。
しかし、これはローマの祭りであり、キリスト教、ましてや聖ウァレンティヌスとは全く関係がありませんでした。
しかし、時代が移り変わり、キリスト教徒が増えてくると、ルぺルカリア祭は古代ローマの神々ではなく、聖ウァレンティヌスを讃えるバレンタインデーへと変化します。
世界各地のバレンタインデー
カトリック教会が普及した地域(主に西欧)
バレンタインデーの起源とされる、カトリック教会が普及した西欧では、2月14日がウァレンティヌスの記念日とされてきました。
しかし、1962~1965年に行われた第2バチカン公会議で、実在が明らかではない人物の記念日は取り除かれることになり、ウァレンティヌスの記念日も消えてしまいます。
それでもバレンタインデーは、恋人や親しい人に贈り物を送る日として定着することになります。
贈り物はチョコレートに限定されているわけではないので、花やカードを送る人もいるそうです。
正教会が普及した地域(主に東欧)
正教会では、聖ウァレンティヌスは2人います。
しかし、2人とも記憶日は7月であり、聖ウァレンティヌスと恋人を関連付ける習慣もありませんでした。
なので、バレンタインデーは元々ありませんでしたが、西欧のバレンタインデーの習慣に企業が乗っかり、プレゼントをする日として「バレンタインデー」が定着している地域もあるそうです。
特徴的な日本のバレンタインデー

先ほど述べたような国々に比べると、日本のバレンタインデーはかなり特色のあるものになっています。
日本でのバレンタインデーのイメージは、「女性が愛する男性にチョコレートを贈る」というものです。
このイメージは日本のチョコレートメーカーによって形作られたと言われていますが、では、最初にこのようなイメージを打ち出したのはどのメーカーだったのでしょうか?
日本で最初にバレンタインデーに関する広告を出したのは、神戸モロゾフ製菓(現在のモロゾフ)です。
その広告がこちら。
あなたのバレンタイン(=愛しい方)にチョコレートを贈りましょう
東京で発行されていた英字新聞に1936年2月12日に掲載されたものです。
これ以降もチョコレートメーカーはバレンタインデーを定着させようと努力するものの、当時は見合い結婚が多く、恋愛結婚が少数派だったこともあり、なかなか普及しませんでした。
これが、1970年代になると、日本は消費社会に突入。
小学生から高校生にかけての若い世代がバレンタインデーの習慣を取り入れるようになり、現在のような日本のバレンタインデーのイメージが出来上がったと言われています。
まとめ
- バレンタインデーは、古代ローマの神々の祭りが、聖ウァレンティヌスを讃えるための記念日に変化したものだった。
- 西欧ではバレンタインデーには、恋人や親しい人に贈り物をする習慣がある。
- 日本のバレンタインデーはチョコレートメーカーの販促もあり、独自の発展を遂げて現在のような形になった。
バレンタインデーにチョコをあげて付き合った、みたいな話を都市伝説だと思っているのは私だけでしょうか…。