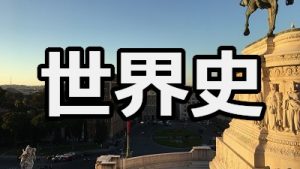こんにちは、歴くまです!
平安時代の文学を彩った才女たち、中でもパッと思い浮かぶのは紫式部と清少納言の二人でしょう。
しかし、この二人以外にも、才能あふれる女性たちは何人もいました。
今回は、平安時代の国風文化を支えた女性たちについて、見ていきましょう。
藤原道綱母
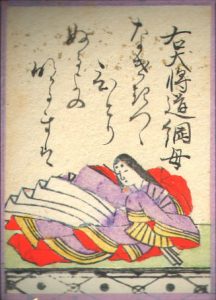
藤原道綱母
藤原道綱母は、藤原兼家の妻で、藤原道綱の母にあたる人物です。
藤原兼家は、あの藤原道長の父であるので、藤原道綱母は道長の継母になります。
彼女が後世に残した作品が、『蜻蛉日記』です。
蜻蛉日記には、夫である兼家との結婚生活、兼家の妻妾への嫉妬、彼女の子道綱の成長の記録などが記されており、当時の貴族の妻の生活を知る上での貴重な資料と言えるでしょう。
例えば、天暦9年(955年)9月、彼女は次のように綴っています。
さて九月ばかりになりていでにたるほどにはこのあるを手まさぐりにあけてみれば人のもとにやらんとしけるふみあり
さて、9月ごろになって、兼家が出ていったときに文箱があるのを手慰みに開けてみると、他の女に宛てた手紙がある。
これは…、兼家には他に女ができたようです。
さらに10月になると、
なげきつゝひとりぬるよのあくるまはいかにひさしきものとかはしる
嘆きながら、一人で寝る夜が明けるまでの間は、どんなに長いものか分かりますか。
道綱を出産して、すぐに他の女をつくった兼家が藤原道綱母を訪ねてきますが、彼女は兼家を中に入れず、立ち去ってからこの歌を送ったと言います。
彼女がマタニティーブルーや産後うつになっていたかは定かではありませんが、そんな時期に他の女のもとへ出かける兼家を拒む気持ちが前面に出ている歌ですね。
菅原孝標女

菅原孝標女の先祖・菅原道真
菅原孝標女は、上総国・常陸国の受領を務めた菅原孝標の娘として生まれます。
孝標は「学問の神様」として今も親しまれている菅原道真の玄孫(孫の孫)にあたり、菅原孝標女は道真の来孫(玄孫の子)になります。
また、彼女の母の姉は藤原道綱母、つまり藤原道綱母は伯母にあたります。
彼女が書いていたのは『更科日記』、彼女が13歳の寛仁4年(1020年)から、52歳頃の康平2年(1059年)までの約40年間について、回想録の形で綴られています。
『源氏物語』を読みふけり、物語の世界に憧れを抱いていた少女時代、祐子内親王家への出仕、橘俊通との結婚と出産、夫俊通の病死と子供たちの独立と、平安時代に生きた女性の一生が詰まって綴られています。
彼女が生まれたのは平安時代の最盛期であり、それから徐々に戦乱の世へと移っていくという過渡期にありました。
『更科日記』もそのような時代背景を踏まえ、少女時代を良き時代として思い出すと共に、現在の孤独な我が身を綴っています。
和泉式部

和泉式部
和泉式部は、越前守である大江雅致の娘として生まれます。
成長した和泉式部は和泉守・橘道貞の妻となり、夫と共に和泉国へ行きます。
この夫の任国「和泉」と父の官名「式部」を合わせたものが、彼女の女房名「和泉式部」となりました。
彼女は道貞との間に娘の小式部内侍を儲けますが、夫婦仲は徐々に悪くなり、帰京後も道貞とは別居状態であったそうです。
そんな和泉式部ですが、恋多き女性であったようで、冷泉天皇の第三皇子・為尊親王との熱愛が噂されるようになります。
父の雅致は、身分違いの恋であるとして、彼女を勘当してしまいました。
その後、為尊親王は病死してしまいますが、モテる女は辛いもの。
なんと、今度は為尊親王の弟である、敦道親王から求愛を受けるのです!
この敦道親王との恋愛と、和歌のやり取りを綴ったのが『和泉式部日記』です。
敦道親王との子供を儲けた和泉式部でしたが、その敦道親王も若くしてこの世を去ります。
彼女は、最終的には藤原道長の勧めで、道長の家司(家政を掌る職員)の藤原保昌と再婚し、丹後国へと行くことになります。
赤染衛門

赤染衛門
赤染衛門は、赤染時用の娘として誕生しますが、これには裏話があります。
彼女は、実は平兼盛の子供なのではないか、という説があるのです。
なぜなら、時用の妻の前夫は兼盛で、兼盛と婚姻していたころに懐妊したのが赤染衛門ではないか、と言われているのです。
当時、これは裁判沙汰にもなり、兼盛は娘の親権を主張するも、退けられてしまいます。
赤染衛門は、文書博士の大江匡衡と結婚。
夫婦仲はとても良かったようで、そのおしどり夫婦ぶりから匡衡衛門と呼ばれていたそうです。
なんか夫婦漫才師みたいですね(笑)
恋多き和泉式部が情熱的な歌風であったのに対し、夫を一途に愛した赤染衛門は穏健で典雅な歌風と評価されています。
赤染衛門の代表作としては、歌集の『赤染衛門集』がありますが、平安時代の歴史物語『栄花物語』正編30巻の著者であるとも言われています。
まとめ
平安時代の国風文化を支えた女性たちを紹介しましたが、いかがだったでしょうか?
紫式部と清少納言が有名ですが、彼女たち以外にも教養の深い女性たちが多くいたことが分かります。
しかし、平和を謳歌していた時代は終わりを告げ、徐々に武士が台頭し、戦乱の世へと繋がっていくのです。